
MEMORANDUM-陶房雑記帳-2011年11月
■錦江飯店のビアマグ
だいぶ前のことですが、上海の錦江飯店のバーを友人と訪れビールを注文したときに出てきた容器が風変わりな形をしていました。通常のジョッキともマグカップとも異なる象のような形をした陶製のカップで、鼻の部分に指を掛けて飲むと結構飲みやすいものでした。
上海のダウンタウンにある錦江飯店は海沿いの外灘にある和平飯店とともに上海を代表する老舗のホテルです。バーも重厚な板張りのクラシックな雰囲気だったような記憶があります。ビールを何杯か飲んで店を出るときに陶製カップが興味深いので記念に貰えないか、とお願いしたら気前良くどうぞとペアーでいただいた。(私の経験では東南アジアの人たちは比較的おおらかで、頼むと簡単に了解してくれる。日本ではなかなかそうは行かないようです。例えば、ホテルオークラのバーでグラスが気に入ったから持って帰って良いかと頼めば、多分断られるでしょう。)
今、久しぶりにこのマグカップを眺め、作った人はどういうつもりで作ったのかしら、と想像しています。ビールを飲むための器として作ったのか、それとも他の目的で作ったものが結果としてビールに使われているものなのか。
いずれにしても、その陶芸家(デザイナー)はかなり独創的な方だったと思っています。毛沢東、周恩来、鄧小平というような中国の指導者が定宿にして、アメリカの大統領なども宿泊したことがあるといわれる錦江飯店のご用達ですから、いろいろと知恵を絞ったに違いありません。
ビアマグにしても、徳利にしても、ぐい呑みにしても、酒器はいろいろと工夫を凝らして“普通でないけれど飲みやすい”ものが興味深いですね。酒は楽しむもの、という考えが容器にも反映されているわけです。
陶芸だけではありませんが、一生懸命やればやるほど作風もワンパターンになりがちなので、時々変わったものを見て頭を柔軟にしてアイデアを発見することが、創作活動をする者にとっては大切だと思っています。
 私は用事があって東京や横浜などに出かける時には、ちょっと早めに出かけてデパートの美術画廊や食器売り場をぶらぶらするようにしています。ぶらぶらきょろきょろしていると必ず何か作陶のヒントがあるものです。
私は用事があって東京や横浜などに出かける時には、ちょっと早めに出かけてデパートの美術画廊や食器売り場をぶらぶらするようにしています。ぶらぶらきょろきょろしていると必ず何か作陶のヒントがあるものです。
(付記)和平飯店はその後改装してフェアーモントピースホテルという名前で営業しているようです。ホテル内にある有名なオールドジャズバーも健在のようです。(2011.11.17)
↑錦江飯店のビアマグ
■茶碗を作る
陶芸の世界で茶碗は難しい、という話をよく聞きます。私もそう思います。
茶碗はただ作るだけなら簡単で、轆轤を回せばいくらでも出来てしまいます。陶芸を始めた頃はよく茶碗を作って焼き上がりをしげしげ眺めて一人で満足していたものでした。しかし、幸か不幸か家内が裏千家茶道の末端にいるものですから、出来上がりにいろいろな注文がついてくる。
“口縁を茶巾で拭きにくい”“重くて持ちにくい”“高台をきれいに削りすぎている”、挙句の果ては“景色が良くない”等々。そして茶道の作法や茶碗作りのしきたりを知るにつけ、制約された中で作るのに嫌気がさしてきた、というか、ますます難しく感じるようになってしまいました。
そんなわけで今は大ぶりの湯飲み茶碗かご飯茶碗を作るくらいの気軽な気持ちで作って、結果、出来上がりがお茶席で使えるようであれば、それで良いではないか、と思うようにしています。いい茶碗を作ろうとか、形の良いものを作ろうとか、欲張らないでなるべく素直な気持ちで茶碗を作る、という姿勢が必要なのかなと思っています。しかし、どんな芸事でもそうだと思いますが“良い物を作りたい”“良いプレーをしたい”という意欲がなければ向上はないと思います。難しいですね。
先日、京都に出かけたついでに楽美術館に立ち寄って数々の名碗を鑑賞してきました。楽美術館は楽家や永楽家の歴代の茶器・茶碗を展示している小さな美術館です。
楽家歴代の茶碗は黒楽・赤楽等々、侘びを追及して少ない装飾の中で深みを表現していると感じました。一方、永楽家の茶碗は雅(みやび)を表現して色絵を駆使したものが多く、特に16代永楽即全(善五郎)の色絵紅白梅絵茶碗は華やかな中に重厚感があり素晴らしいものでした。
 茶碗の世界ではよく“一楽、二萩、三唐津”という言葉を聞きます。茶席には楽の茶碗が一番似合う、というような意味だと思っていますが、目の前にある茶碗をよいと思うか、悪いと思うかは、見る側の心の持ち方にもよるのだろうと思っています。私にとっては有名な(高価な)茶碗でなくても素晴らしいと思える茶碗はいくつもあります。
茶碗の世界ではよく“一楽、二萩、三唐津”という言葉を聞きます。茶席には楽の茶碗が一番似合う、というような意味だと思っていますが、目の前にある茶碗をよいと思うか、悪いと思うかは、見る側の心の持ち方にもよるのだろうと思っています。私にとっては有名な(高価な)茶碗でなくても素晴らしいと思える茶碗はいくつもあります。
(2011.11.8)
楽美術館の前で→
■どぶろくの甕(かめ)
私の生家の物置に長年置き去りにされていた陶製の甕が、今私の家のテラスにおいてあります。もともとどこで作られ何に使われた甕かもわかりません。静岡あたりでお茶を保存する容器だったのか、あるいは薩摩のほうで焼酎の容れものとして作られたものか、濃い茶色の比較的大きな甕です。出来上がりは薄く円く轆轤の腕が良い陶工が成形したのだと思います。どのくらい入るか一升瓶に水を入れて試してみたら10本分入りました。
私が小学校に入学したばかりの10歳前後のころだと思いますが、この甕は田舎の家の物置小屋の土間に埋めてあり、中にはどぶろく(濁り酒)が入っていました。甕の口元だけが地面に出ていて栓がしてあったのですが、そこから甘酸っぱいどぶろくの匂いが漂っていました。
当時、両親や祖父母に確認した記憶はありませんが、戦後の食料や物資が不足していた時代です、多分密造酒だったのでしょう。私の父母兄弟はほとんど飲めないタイプで、唯一記憶にあるのは祖父が毎日晩酌していたことくらいです。
おそらくこの甕の中にあったどぶろくは祖父が晩酌用に密かに作っていたものだと思います。子供心に甕の口元から流れるどぶろくのほのかな匂いを魅惑的に感じたものです。今私の家のテラスにおいてある陶製の甕は一部が傷ついてほとんど価値のないようなものですが、私にとってはいろいろな懐かしい思い出を含んでいます。
同じような年のころに生家の近くの米軍厚木基地(飛行場)のお祭りに連れてゆかれ、米兵が飲み干し捨てた缶ビールの空き缶からほろ苦い香りが流れていた記憶があります。(当時、米軍基地は近隣の住民のために年に一度その一部を解放してお祭りのようなことをしていました。)そのころは未だ日本には缶ビールはなかったと思いますが、何となくアメリカという国を刺激的に感じさせたビールの空き缶の匂いでした。
子供のころに体験したどぶろくとビールの空き缶の匂いとが私を酒好きにしたのかもしれません。私は酒の量はいけませんが、基本的には飲めるほうです。
 ビール会社に勤務していた頃にアルコール分解酵素の量を測る検査をしたことがありますが、その結果“アルコールに強いグループ”に分類されたことがありました。たぶん私は祖父の遺伝子を引き継いでいるのだと思っています。 (2011.11.8)
ビール会社に勤務していた頃にアルコール分解酵素の量を測る検査をしたことがありますが、その結果“アルコールに強いグループ”に分類されたことがありました。たぶん私は祖父の遺伝子を引き継いでいるのだと思っています。 (2011.11.8)
どぶろくが入っていた甕 →
■清水焼ぶらり散歩
京都で仕事していたころの仲間が集まった機会に、久しぶりに清水焼をぶらりと散歩し見物してきました。
まずは、山科清水焼団地の富田玉凰陶苑を訪問。玉凰さん(伝統工芸士)はそう思っていないかもしれませんが、私が陶芸を志した40歳前後の頃、もっとも私に影響を与えてくれた陶芸家です。そのころ週末にはよく陶苑にお邪魔して雑談し、いろいろ教えていただきました。今も使っている私の赤土は玉凰さんの作品と同じ業者から取り寄せています。茶碗の高台をざっくり削るには割れた陶片の先を使うといいですよ、と言われたことが記憶に残っています。
奥さんも気さくな方で気に入った作品を安くしていただいたおかげで、わが家には玉凰さんの作品がたくさんあります。茶碗・水差し・花瓶、そしてコーヒーカップやワインカップなどの小物まで。特に乾山写しの梅絵茶碗は本物よりもすばらしいのでは(本物に触れたことはありませんが・・・)と思っています。また頂いた茶器の桐箱には素晴らしい達筆の上書きがされています。
平成17年には勲章(瑞寶単光章)を天皇陛下から授与され、今年80歳になられるとのこと。残念ながら最近は体調を崩され病院通いの日々とのことで創作活動はほとんどされていないようです。店先で玉凰さん、奥さんと昔ばなしをして娘さんが絵付けをされたという手びねり徳利を記念に頂いて失礼しました。
富田玉凰陶苑から歩いて数分のところにあるギャラリー「洛中洛外」では優雅なスペースでお茶をご馳走になり多くの作品を鑑賞しました。
京都にゆかりのある作家の作品を総合的に紹介している広いギャラリーです。若手新進の陶芸家の作品あり、人間国宝クラスもあり、多くの陶芸家が切磋琢磨し、しのぎを削っている京都はやはり日本の陶芸の中心的な場所であると改めて感じます。
清水焼団地からバスで市内へ。途中、五条坂で下車。五条坂界隈は1965年以降に山科に清水焼団地ができて多くの陶芸家が移住するまでは清水焼発祥の地として賑わったところです。
清水六兵衛さんの工房ギャラリーを覗きました。六代目清水六兵衛さん(1901~1980年)は、陶の表面に日本的情緒ある風情をダイナミックに表現している私の憧れの陶芸家です。しかし、当代(8代)の作品は幾何学的造形を主体としたものが多く、六代目に憧れを抱いているものとしてはちょっと残念でした。
 五条坂界隈には普段使いの陶磁器を売る、いわゆる“茶碗やさん”が軒を並べています。そんな店をいくつか覗いて“掘り出し物”を探しながら歩きました。今回久しぶりの清水焼めぐりは、何となく時代の流れを感じるものとなりました。 (2011.10.22)
五条坂界隈には普段使いの陶磁器を売る、いわゆる“茶碗やさん”が軒を並べています。そんな店をいくつか覗いて“掘り出し物”を探しながら歩きました。今回久しぶりの清水焼めぐりは、何となく時代の流れを感じるものとなりました。 (2011.10.22)
玉凰さんの水差しと
娘さんの手びねり徳利 →
■土井コレクション展
文京区春日の礫川(こいしかわ)浮世絵美術館で開催されている、土井コレクション展「伝統木版画の彫と摺」を観てきました。土井コレクションの土井利一さんは私の20年来の友人で、知る人ぞ知る浮世絵版画研究家でコレクターでもあります。
今回のコレクション展では、明和5年(1765年)の錦絵誕生以来卓越した彫摺(彫り摺り)職人たちによって継承され制作されてきた数多くの逸品コレクションが展示されていました。土井さんの解説によれば、浮世絵は版元・絵師・彫師・摺師の協同作業で制作されてきたにもかかわらず、彫師・摺師の名前が表記されることはまれで、彫師も摺師も徒弟制度のもとで長年の厳しい修行に堪えて伝統技術を継承してきた、ということです。
私は昨年、中国景徳鎮で陶磁器の製作現場を見てきて、見事に分業で成り立っているのを思い出しました。やはり高度な芸術の表現はそのパーツごとの習熟によってなし得るのでしょか?
私は版画に関しては土井さんのように詳しくなく全くの素人ですので、彫り、摺り、という(比較的地味な)作業段階に関してはその良さがわかりません。やはり結果である作品を見て単純に良さを感じます。
前回の土井さんのコレクション展で初めて知った川瀬巴水(1883年~1957年)の作品は素晴らしいと思っています。今回展示されていた川瀬巴水の作品「夜の池畔(不忍池)」を観ていると、灯りの赤と黄、そして暗い部分の青と黒が本当に印象的に使われています。(作品としては全く異なりますが、有名なゴッホの「夜のカフェテリア」から受ける印象に似ています。)その他、雪景色の白い色、夜明け前の空を見事に表現したブルー。
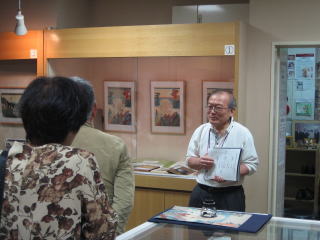 川瀬巴水の作品はどれを見ても、その色彩の表現が詩情豊かで昔どこかで見たような風景だなと感じさせられます。
川瀬巴水の作品はどれを見ても、その色彩の表現が詩情豊かで昔どこかで見たような風景だなと感じさせられます。
陶芸における作品の発色も、見る人に“何か”を感じさせることが大切であると改めて感じた土井コレクション展でした。(2011.10.15)
解説をする土井さん→

神奈川県藤沢市高倉815-2
(小田急線長後駅東口徒歩7分)