
MEMORANDUM-陶房雑記帳-2012年6月
■「故郷忘じがたく候」
だいぶ前に読んだ司馬遼太郎の短編「故郷忘じがたく候」を読み直しました。
この小説は、薩摩焼の人間国宝沈壽官の祖先が鹿児島の今の地に連れてこられてからの物語です。私が沈壽官窯を訪問したのは20年ほど前のこと、第14代のころでしたが、この短編小説も14代沈壽官とのインタビューをもとに司馬遼太郎の紀行文的な短編小説として、構成されています。
沈壽官窯の歴史についてはホームページ「沈家のあゆみ」に詳しく書かれています。以下、抜粋。
“慶長三年(1598年)、豊臣秀吉の二度目の朝鮮出征(慶長の役)の帰国の際に連行された多くの朝鮮人技術者の中に、初代沈当吉はいた。(中略)薩摩の勇将島津義弘によって連行された朝鮮人技術者達(製陶、樟脳製造、養蜂、土木測量、医学、刺繍、瓦製造、木綿栽培等)は、見知らぬ薩摩の地で祖国を偲びながら、その技術を活きる糧として生きていかねばならなかった。陶工達は、陶器の原料を薩摩の山野に求め、やがて薩摩の国名を冠した美しい焼物「薩摩焼」を造り出したのである。(中略)沈家は代々、薩摩藩焼物製造細工人としての家系をたどり三代 陶一は藩主より陶一の名を賜わり、幕末期には天才 十二代 壽官を輩出した。”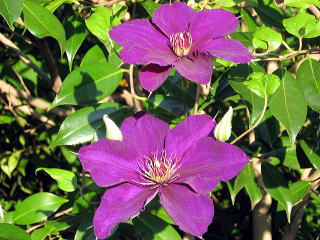
小説の中で印象的だったのは、若いころの14代が父親である13代に美術学校へ行こうか?と相談を持ちかけたときの13代の答えです。以下、抜粋。
“一人息子が美術学校へゆくとなれば家業柄、当然よろこんでいいところかもしれなかったが、13代は同意せず、「どうせ村に帰ってくれば一生茶碗屋をやらねばならぬ者が、せめて若いころだけでも茶碗と縁のないことをやって息をぬいておかねば、せっかく生まれてきたわが身が可哀そうすぎる」といった。”
結果として14代は早稲田大学政経学部に入学したということですが、美術だけに拘らない13代の懐の深さと人間の大きさを感じさせられます。
それにしても作家司馬遼太郎の綿密な取材と取材情報をもとにした想像力と創造力は素晴らしいものだと思います。(2012.6.20)
■藤沢三田会アート展
今年も6月26日から恒例の藤沢三田会アート展が市民ギャラリーで開催されます。絵画・書道・写真・工芸など多くの分野から計35名の力作が発表されます。趣味で楽しんでおられる方からプロ顔負けに活躍している方まで多彩なメンバーです。私の受け持ちは陶芸分野ですが他の分野の作品からもいろいろな刺激を受けて有意義な楽しい会です。今年は第9回になりますが私は第2回から参加していますので8回目の出展です。
今年は案内はがきに私の陶芸作品を採用していただいたので、これまで以上に責任を感じています。
今年は「香る陶」をテーマに香炉や蚊取り線香入れなどを中心に20点ほど出展します。
↓昨年のアート展の出展作品
 香炉というと寺院のような厳粛な場所で使われたり床の間に置かれたりと、一般的には上品ですました感じのものが多いのですが、製作にあたっては気軽に使っていただけるような雰囲気を表現できるように心がけました。
香炉というと寺院のような厳粛な場所で使われたり床の間に置かれたりと、一般的には上品ですました感じのものが多いのですが、製作にあたっては気軽に使っていただけるような雰囲気を表現できるように心がけました。
また蚊取り線香入れはもともと庶民的なものですが、イスラム寺院をイメージして装飾的なものを作ってみました。
個展でもグループ展でも開催日(目標)が決まると励みが出ます。
私にとって作品の発表の目的は、やはり皆さんに広く自分の作品を見ていただき評価していただいて、今後の作陶の参考にする、励みにする、というところにあります。
同じ自分の作品でも自分で観たものと他人から観られるものとでは印象(評価)が異なります。自己評価はどうしてもその作品が出来上がった背景や思い入れがありますから手前勝手な評価になりがちですが、他人の評価は“いま目の前にある作品”に対する評価だけですから、自己評価・自己満足とは異なったものになります。(もっとも正直に評価してくれる人は少ないですが・・・。)
どんな芸でもそうでしょうが「観られる」ことを意識して行われます。そして観た人に何かを感じていただきたい、と思って私は製作活動を続けています。
※アート展の発表作品は7月上旬に当ホームページ「ギャラリー」で紹介予定です。(2012.6.7)
■浮月楼の屋根瓦
5月24日夕、名古屋で仕事をしていたころの仲間7名が奥さん同伴で集まりました。1966年ころに初めて会ってからのお付き合いですから永年の友人ばかりです。場所は静岡市の料亭浮月楼、駅から歩いて五分程度の繁華街の中にあるオアシスのような場所です。
浮月楼は15代将軍徳川慶喜が大政奉還後の明治2年から20年にわたり住んだという旧居後にあります。回遊式の池を囲んだ庭は当時日本随一といわれた京都の庭師小川治兵衛の作庭で、その庭に面して徳川慶喜邸の面影を残した浮月楼の和風建築が建てられています。
宿泊は浮月楼に併設されたホテル「GARDEN SQUARE」。
 チェックインを済ませ部屋に入ると窓一面に見えるのは浮月楼の屋根瓦。銀鼠色のいぶし瓦が新緑に映えて印象的でしばらく眺めて写真に収めました。この屋根瓦の下の部屋で私たち14名が食事をし旧交を温めたのですが、前日(5月23日)には将棋の名人戦第4局(羽生名人VS森内名人)が開催されていたということでした。
チェックインを済ませ部屋に入ると窓一面に見えるのは浮月楼の屋根瓦。銀鼠色のいぶし瓦が新緑に映えて印象的でしばらく眺めて写真に収めました。この屋根瓦の下の部屋で私たち14名が食事をし旧交を温めたのですが、前日(5月23日)には将棋の名人戦第4局(羽生名人VS森内名人)が開催されていたということでした。
浮月楼の屋根瓦→
屋根瓦(銀鼠色のいぶし瓦)の整然と並んだやわらかい文様は、絵画や写真などによく使われていますが、ホテルの窓からゆっくりと眺めることができ改めてその落ち着いた美しさを感じました。
京都の街並みの瓦屋根を描いた日本画や版画を見た記憶がありますし、外国の瓦屋根(たとえばスペインの陶器瓦など)を描いた絵もいくつかあったと思います。
屋根瓦の風景としての美しさとは別に、瓦そのものも美術品ではないかと思い調べると、ありました! 生産量日本一を誇る三州陶器瓦の中心地、愛知県高浜市には「やきものの里・かわら美術館」が1995年にオープンしていることがわかりました。機会を見てぜひ訪問したいと思っています。
日本ではタイルとか瓦などの陶磁製品は建材として扱われるだけのことが多いようですが、美術品としてももっと注目されてもいいのではないかと改めて思います。
例えば一つ一つの瓦の形を利用して陶芸の表現ができないか?のんびりとホテルの窓から銀鼠色の瓦屋根を眺めてまた作陶のヒントを得たような小旅行でした。(2012.5.31)

神奈川県藤沢市高倉815-2
(小田急線長後駅東口徒歩7分)